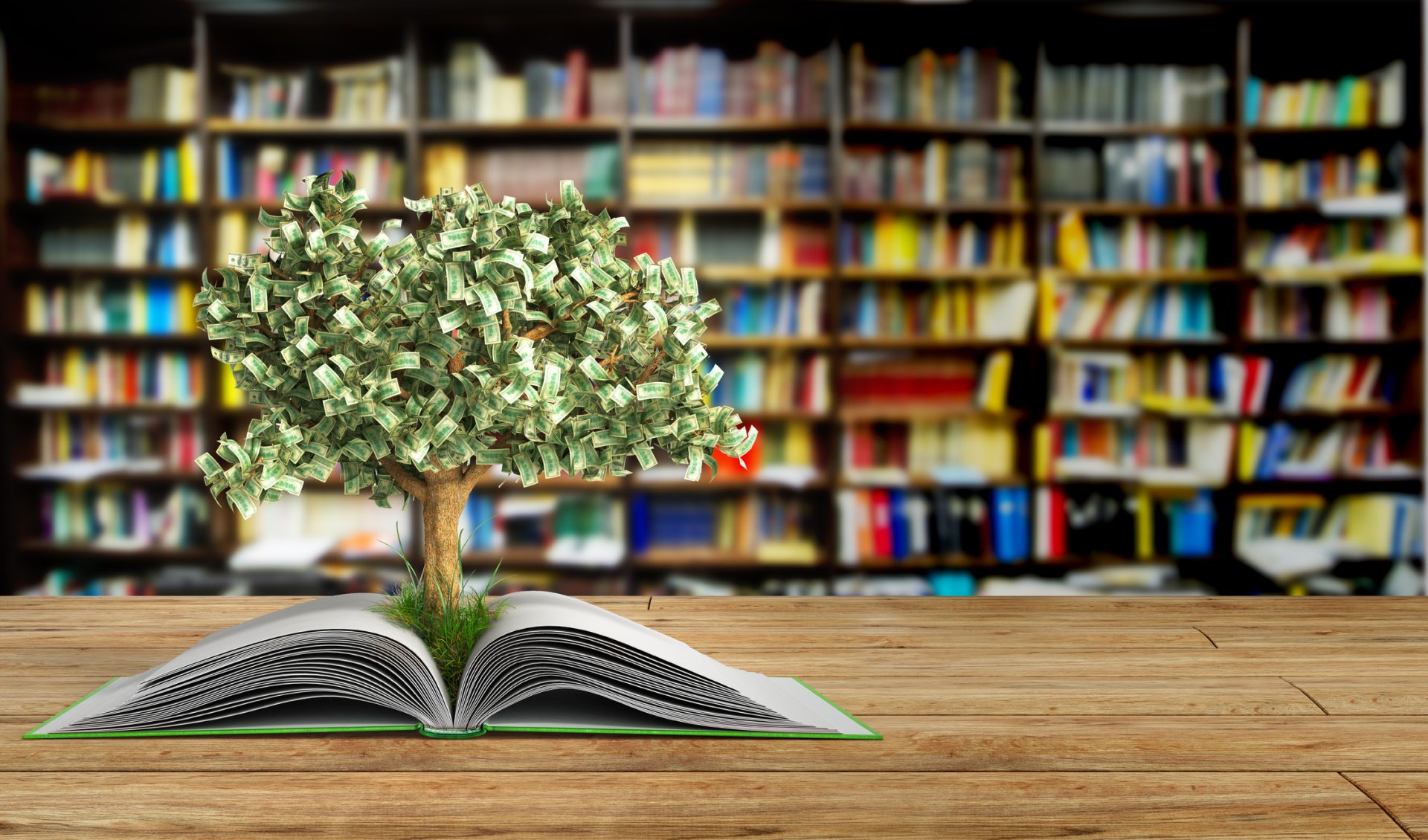グリーン成長戦略とは、経済活動を通じて環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するための政策指針です。これは、環境保護と経済成長を相反するものではなく、相互に促進する力として捉えることに核心があります。
この記事では、グリーン成長戦略の概要から具体的な内容、取り組み事例についてわかりやすく解説します。
グリーン成長戦略の基本
グリーン成長戦略とは、地球温暖化への対応を経済成長の機会と捉え、「経済と環境の好循環」を作り出すことを目指す日本の産業政策です。日本政府は2021年6月18日にこの戦略を策定し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた実行計画を産業政策とエネルギー政策の両面から示しています。
これは、温室効果ガス削減の取り組みを経済成長の足かせと捉えるのではなく、むしろ企業にとっての成長機会として捉え、脱炭素経営を後押しすることを目的としています。
グリーン成長戦略の目的
グリーン成長戦略の目的は、2050年カーボンニュートラルに伴う温室効果ガス排出量実質ゼロの達成と、経済成長の同時実現です。日本は2050年までにカーボンニュートラル社会を実現するにあたり、「2030年度における温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける」という目標を掲げています。この目標達成には、産業界のCO2排出量削減が不可欠であり、グリーン成長戦略では、税制支援や各種補助金などを通じて、民間企業が脱炭素経営を実行しやすい環境を整備し、イノベーションの創出や産業構造の転換を促すことを目指しています。
グリーン成長戦略が策定された背景
グリーン成長戦略が策定された背景には、2020年に当時の菅義偉内閣総理大臣が「2050年までのカーボンニュートラル実現」を宣言したことがあります。これは、地球温暖化問題が深刻化する中で、日本が国際社会の一員として脱炭素社会の実現に貢献する決意を示したものです。
この宣言を受け、経済産業省が中心となり関係省庁と連携し、2020年12月25日に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。これまでの「温暖化対策は経済活動の負荷」という考え方を転換し、積極的に温暖化対策を行うことが産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想のもと、具体的な実行計画が盛り込まれました。この戦略は、2021年6月18日に改訂され、より具体的な目標と取り組みが示されています。
グリーン成長戦略と私たちの生活
グリーン成長戦略は、企業の取り組みだけでなく、私たちのライフスタイルにも大きな影響を与えます。
例えば、自動車・蓄電池分野では、乗用車の新車販売が2035年までに全て電動車になることを目指しており、充電インフラの整備も進められています。これにより、ガソリン車と同等の利便性が確保され、私たちの移動手段が大きく変化するでしょう。
また、住宅・建築物分野では、省エネ性能の高い住宅や建築物の普及が推進され、家庭でのエネルギー消費が削減されることで、電気料金の負担軽減が期待されます。
さらに、食料・農林水産業分野では、化石燃料を使用しない園芸施設や次世代有機農業技術の確立、農林業機械・漁船の電化・水素化が進められ、私たちの食生活や食料生産のあり方も変化します。
半導体・情報通信分野では、次世代パワー半導体の実用化やグリーンデータセンターの国内立地により、家電の電気料金負担が軽減されるだけでなく、自動運転や遠隔手術といった新たなデジタルサービスが実現し、私たちの生活の利便性が向上します。
ライフスタイル関連分野では、シェアリングエコノミーの拡大や、製品の長寿命化・再利用の促進など、持続可能な消費行動を促す取り組みが進められます。
これらの変化は、私たちが日々の生活の中で環境に配慮した選択をしやすくなるだけでなく、新たなサービスや製品の登場により、より豊かで便利な社会が実現されることを目指しています。
グリーン成長戦略における主要14分野
グリーン成長戦略では、2050年カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立を目指し、特に重要な14分野が特定されています。これら14の分野は、エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業の3つの大きなカテゴリーに分類されます。それぞれの分野で、具体的な目標設定と今後の取り組みが示されており、政府はこれらを達成するための政策支援を集中させています。
エネルギー関連分野
エネルギー関連分野は、グリーン成長戦略の中でも特に重要な柱であり、脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの促進と電気供給の脱炭素化を最重要課題としています。この分野は「洋上風力・太陽光・地熱」「水素・燃料アンモニア」「次世代熱エネルギー」「原子力」の4つの重点分野に細分化され、それぞれに具体的な実行計画が定められています。
1 洋上風力・太陽光・地熱
洋上風力・太陽光・地熱は、再生可能エネルギーの中でも特に重要な分野として位置づけられています。洋上風力発電では、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kWから4,500万kWという具体的な導入目標を掲げ、国内外からの投資を呼び込むことを目指しています。同時に、国内調達比率を60%に高めることで、サプライチェーンの強化も図られます。
太陽光発電については、2030年の発電コスト目標を14円/kWhに設定し、将来的な世界市場の獲得も視野に入れています。地熱発電では、次世代型地熱発電技術の開発を推進し、国内での市場規模の拡大を目指しています。
これらの取り組みは、技術開発と地域社会との共通理解を目標の柱とし、自然公園法や温泉法の運用見直しを通じて、開発を加速させていく方針です。
2 水素・燃料アンモニア
水素・燃料アンモニア分野は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた重要な次世代エネルギー源として位置づけられています。水素は、燃焼時にCO2を排出しない特性を持ち、様々な資源から製造可能です。今後の取り組みとして、2030年までに国内導入量を最大300万トン、2050年には2,000万トン程度に拡大し、供給コストを20円/Nm3以下に抑えることで、化石燃料と同等の競争力を持つ水準を目指しています。これには、輸送・貯蔵技術の早期商用化によるコスト低減や、水素輸送関連設備の大型化、国際標準化推進が含まれます。
燃料アンモニアは、燃焼時に炭素を含まないためCO2を排出せず、エネルギーキャリアに優れているという特徴があります。2030年には石炭火力の20%を燃料アンモニアに代替することを目指しており、国内外での技術開発と早期実用化が進められます。2050年には、化石燃料に対して十分な競争力を有する水準を目指すとともに、サプライチェーン全体のコスト低減を図ることで、幅広い産業での利用拡大を目指しています。
3 次世代熱エネルギー
次世代熱エネルギー分野では、2050年までに都市ガスのカーボンニュートラル化を目指しています。主な取り組みとして、合成メタン(メタンとCO2から生成される燃料)の既存インフラへの注入率を、2030年には1%、2050年には90%まで引き上げる計画が挙げられます。これにより、新規インフラ投資による追加負担を回避しつつ、円滑な脱炭素化を実現することを目指しています。また、合成メタンの供給コストをLNG価格と同等にするための革新的な技術開発や安価な海外サプライチェーンの構築を進め、2050年までに40~50円/㎥のコストを目指します。家庭においては、年間約14,000円の追加負担を回避できると期待されており、総合エネルギーサービス企業への転換も図られます。
これは、ガスコジェネレーションの導入促進による熱の有効利用、分散型エネルギーシステムの構築、デジタル技術を活用した地域における最適なエネルギー制御の実現を目指すものです。
4 原子力
原子力分野では、安全性の向上を最優先としつつ、次世代炉の開発と利用を進める方針が示されています。具体的には、国際連携による高速炉開発を着実に推進し、2030年までに小型モジュール炉技術や高温ガス炉における水素製造に係る要素技術の確立が目標とされています。高温ガス炉は、1,000度程度までの熱を取り出すことのできる高温原子炉であり、大量かつ安価なカーボンフリー水素の製造技術確立に貢献が期待されます。また、原子炉を活用して生成可能な放射性医薬品材料の活用も推進され、がん治療などの医療分野への応用が期待されています。
原子力技術の発展は、安全性と環境負荷低減を両立しながら、エネルギー供給の安定化と技術革新を進める重要な要素と位置づけられています。
輸送・製造関連分野
輸送・製造関連分野は、経済活動におけるCO2排出量の削減に大きく貢献する重要な領域であり、グリーン成長戦略の中核を担う7つの重点分野が含まれています。これらの分野は、「自動車・蓄電池」「半導体・情報通信」「船舶」「物流・人流・土木インフラ」「食料・農林水産業」「航空機」「カーボンリサイクル・マテリアル」と多岐にわたり、それぞれの産業で脱炭素化に向けた具体的な取り組みが計画されています。
5 自動車・蓄電池
自動車・蓄電池分野は、輸送部門の脱炭素化において極めて重要な役割を担っています。グリーン成長戦略では、乗用車の新車販売について、2035年までに電動車(電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車)100%を実現するという意欲的な目標が掲げられています。商用車に関しても、小型車は2030年までに電動車20~30%、2040年までに電動車・脱炭素燃料車100%の導入を目指し、大型車は2020年代に5,000台の先行導入を計画しています。
これらの目標達成には、高性能な蓄電池の生産能力拡大が不可欠です。政府は、2030年までに国内の車載用蓄電池の製造能力を100GWhまで高めることを目指しています。また、家庭用・業務用の蓄電池についても、2030年までに累積導入量を約24GWhに増やすことが目標とされています。充電・充てんインフラの整備も加速され、2030年までに公共用の急速充電器3万基を含む合計15万基の充電設備を設置し、ガソリン車と同等の利便性を実現します。水素ステーションも、2030年までに1,000基程度の整備を目指しています。加えて、電動車を「動く蓄電池」として活用し、平時にはスマートシティの高度化に、災害時にはレジリエンス向上に貢献することも期待されています。
6 半導体・情報通信
半導体・情報通信分野は、2040年までのカーボンニュートラル実現を目指しています。この目標達成のためには、次世代パワー半導体やグリーンデータセンターなどの技術開発と普及が鍵となります。次世代パワー半導体は、従来のシリコンに加え、窒化ガリウム(GaN)や炭化ケイ素(SiC)といった新素材を活用することで、デバイスの性能向上と電力消費の大幅な削減が期待されています。これにより、家電製品の省エネ化が進み、一般家庭における電気料金の負担軽減に貢献すると予測されています。
また、データセンターの省エネ化も重要な課題であり、光エレクトロニクス技術やエッジコンピューティング技術を活用し、データ処理全体の効率化が図られます。さらに、グリーンなデータセンターの国内立地を推進することで、自動運転や遠隔手術、AR/VRといった新しいデジタルサービスを実現し、私たちの生活の利便性を向上させることを目指しています。これらの取り組みは、単なるCO2排出量削減に留まらず、日本の情報通信インフラの強靭化と国際競争力の強化にも繋がると期待されています。
7 船舶
船舶分野においては、国際的な脱炭素化の潮流に対応し、ゼロエミッション燃料船の開発・導入が重点的に推進されます。具体的には、2030年代までにゼロエミッション船の実用化を目指し、国際海運におけるCO2排出量削減に貢献します。燃料電池技術やアンモニア燃料技術など、新たな船舶用燃料技術の開発と実証が進められ、安全かつ効率的な運航システムの構築が図られます。また、国内造船所の技術開発支援や、国際基準の策定への積極的な貢献を通じて、日本の海運・造船業の国際競争力強化も目指されます。これらの取り組みにより、海運分野からのCO2排出量を大幅に削減し、持続可能な国際物流の実現に貢献していきます。
8 物流・人流・土木インフラ
物流・人流・土木インフラ分野では、運輸部門からの二酸化炭素排出量削減と社会全体の効率化を目指し、多岐にわたる取り組みが展開されています。 具体的には、電動車の普及や排出ガスの削減を目的として電動車に対する高速道路利用時のインセンティブを検討したり、ドローンを用いた物流の実用化を本格的に推進したりしています。土木インフラ分野では、電動、水素、バイオ等の革新的建設機械の導入・普及を進めています。
これらの取り組みを通じて、物流や人流の効率性を高めつつ、社会インフラ全体のグリーン化を進め、持続可能で強靭な社会基盤を構築することを目指しています。
9 航空機
航空機分野では、航空分野からのCO2排出量削減に向けて、次世代航空機の開発と持続可能な航空燃料(SAF:SustainableAviationFuel)の普及が主な取り組みとなります。具体的には、電動化技術や水素燃料技術などを用いた低排出ガス航空機の研究開発を推進し、将来的にはゼロエミッション航空機の実現を目指します。また、バイオマスや廃食用油などから製造されるSAFの生産・供給体制を強化し、航空会社の利用を促進することで、既存の航空機からのCO2排出量削減を図ります。
国際的な枠組みと連携し、航空分野の脱炭素化に向けた技術開発や標準化に貢献することで、日本の航空産業の競争力強化と地球温暖化対策への貢献を目指しています。
10 食料・農林水産業
食料・農林水産業分野では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目指しています。具体的には、化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行を2050年までに目指し、高速加温型ヒートポンプなどの開発を推進します。農業においては、2040年までに次世代有機農業に関する技術を確立し、2050年までに耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大する目標が設定されています。林業分野では、人工林の循環利用を促進し、CO2の吸収・貯留能力を高めることで、ネガティブエミッション(大気中のCO2を吸収・除去する取り組み)の実現に貢献します。また、農林業機械や漁船の電化・水素化についても、2040年までの技術確立を目指し、食料生産のサプライチェーン全体での脱炭素化を推進します。
これらの取り組みは、国民生活の質の向上や健康寿命の延伸にも寄与すると期待されています。
11 カーボンリサイクル・マテリアル
カーボンリサイクル・マテリアル分野は、排出されたCO2を資源として捉え、回収・再利用することでカーボンニュートラル社会の実現を目指す重要な分野です。具体的には、CO2を直接空気から回収するDACCS(DirectAirCapturewithCarbonStorage)技術や、CO2を吸収するコンクリートなどの革新的な技術の開発・実用化を進めます。回収したCO2は、燃料やプラスチック原料、化学品などの製造に利用され、新たな素材として社会に還元されることで、資源循環型社会の構築に貢献します。この分野の取り組みは、鉄鋼や化学といったCO2排出量の多い産業において、製造プロセスの変革を促し、抜本的な排出量削減に繋がることが期待されています。
技術開発に加え、これらの技術を社会実装し、量産化によってコストを低減していくことが重要な目標とされています。
その他重要分野
グリーン成長戦略では、エネルギーや輸送・製造といった主要な産業分野に加えて、私たちの日常生活に密接に関わる「住宅・建築物・次世代電力マネジメント」「資源循環関連」「ライフスタイル関連」の3つの重要分野が「家庭・オフィス関連産業」として位置づけられています。これらの分野は、広範な産業と国民生活全体をグリーン化することで、2050年カーボンニュートラルの達成に貢献することを目指しています。
12 住宅・建築物・次世代電力マネジメント
住宅・建築物・次世代電力マネジメント分野は、家庭やオフィスにおけるエネルギー消費の脱炭素化と効率化を目指す重要な取り組みです。具体的には、2030年までに新築の公共建築物等でZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化、新築住宅でZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化を標準とすることを目指しています。これは、建物の断熱性能向上や高効率設備の導入により、エネルギー消費量を大幅に削減し、再生可能エネルギーの導入を組み合わせることで、エネルギー収支をゼロにすることを目指すものです。また、既存住宅や建築物の省エネ改修も促進し、2050年までにすべての住宅・建築物のZEH・ZEB化の実現を目指します。
次世代電力マネジメントでは、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力系統の安定化と効率的な運用が課題となります。これに対応するため、IoTやAIを活用した次世代スマートメーターの普及や、地域における最適なエネルギー制御システムの構築を進めます。これにより、電力の需要と供給をきめ細かく調整し、電力系統の強靭化と再生可能エネルギーの最大限の活用を図ります。さらに、集合住宅への太陽光発電導入支援や、蓄電池の活用促進も行い、住宅・建設分野からのCO2排出量を削減するとともに、国民生活の利便性向上を目指しています。
13 資源循環関連
資源循環関連分野は、廃棄物の発生抑制、再使用、リサイクルの3R(Reduce,Reuse,Recycle)を徹底し、資源の有効活用と廃棄物からのCO2排出量削減を目指す分野です。具体的には、プラスチック資源循環の高度化や、食品ロスの削減、バイオマス資源の多段階利用の促進などが挙げられます。プラスチックに関しては、リサイクル技術の開発・導入支援や、バイオプラスチックなど環境負荷の低い代替素材への転換を推進します。また、廃棄物発電の効率化や、廃棄物から水素やメタンなどのエネルギーを回収する技術の開発も進められます。これらの取り組みにより、資源の効率的な利用を促進し、天然資源の消費量と廃棄物量を削減することで、循環型社会の構築とCO2排出量削減に貢献します。
14 ライフスタイル関連
ライフスタイル関連分野は、個人の日々の選択や行動が、社会全体の脱炭素化に大きく貢献することを目指しています。具体的には、消費者の環境意識向上を促すための情報提供や、エコ商品の普及促進、シェアリングエコノミーの拡大などが挙げられます。例えば、EVや省エネ家電の普及を促進するためのインセンティブ制度や、食料廃棄の削減に向けた啓発活動、公共交通機関の利用促進などが進められます。また、テレワークやサテライトオフィスの普及を支援し、通勤によるCO2排出量を削減する取り組みも含まれます。
これらの施策を通じて、環境に配慮した選択が当たり前になるような社会を築き、国民一人ひとりがグリーンなライフスタイルを実践できるよう後押しすることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
グリーン成長戦略のポイント
グリーン成長戦略には、その実現に向けた重要なポイントがいくつかあります。まず、対象となる産業の広がりは特筆すべき点です。エネルギー産業だけでなく、輸送、製造、さらには農業やIT産業、住宅、食品といった個人の生活に身近な事業まで、広範囲の産業が対象に含まれています。これは、ほとんどの企業にとってグリーン成長戦略が他人事ではないことを意味しており、自社の業種にどのような目標が掲げられ、税制や規制にどのような変更があるのかを把握することが不可欠です。
対象となる産業の広がり
グリーン成長戦略は、特定の産業に限定されることなく、幅広い産業を対象としている点が大きな特徴です。エネルギー供給の脱炭素化を最重要課題としつつも、洋上風力・太陽光・地熱、水素・燃料アンモニア、次世代熱エネルギー、原子力といったエネルギー関連産業だけでなく、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラ、航空機といった輸送・製造関連産業も対象に含まれています。さらに、食料・農林水産業、カーボンリサイクル・マテリアル、住宅・建築物・次世代電力マネジメント、資源循環関連、ライフスタイル関連といった私たちの生活に密接に関わる分野も網羅されています。
これは、温室効果ガス排出量の8割以上を占める主要な分野に焦点を当て、2050年までに成長が期待され、国際的な競争力を強化できる分野を選定しているためです。つまり、単に環境対策を行うだけでなく、産業全体の構造変革を促し、新たなビジネスチャンスを創出することで、経済と環境の好循環を生み出すことを目指しています。企業は、自社の事業がどの分野に該当するかを把握し、この戦略がもたらす変化に対応していく必要があります。
具体的な目標設定
グリーン成長戦略のもう一つの重要なポイントは、各分野において具体的かつ野心的な目標が設定されていることです。例えば、日本政府は「2030年度における温室効果ガスの排出を、2013年度比で46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける」という目標を掲げています。これは、従来の目標を7割以上引き上げるものであり、容易な達成ではありません。自動車分野では、乗用車の新車販売を2035年までに全て電動車にするという具体的な目標が示されています。また、水素の導入量や供給コスト、再生可能エネルギーの導入目標など、各重点分野で数値目標や工程表が明示されています。
これらの目標は、現時点の技術レベルでは達成が困難とされるほど高く設定されており、技術革新を促すための強いメッセージとなっています。政府は、これらの目標達成を後押しするため、2兆円規模の「グリーンイノベーション基金」を創設し、企業の研究開発や設備投資を支援しています。このように具体的な目標が設定されていることで、企業は自社の取り組みの方向性を明確にしやすくなり、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、ビジネスモデルの変革を加速させることが求められています。
グリーン成長戦略と日本の未来
グリーン成長戦略は、2050年カーボンニュートラルという壮大な目標の達成を通じて、日本の未来に大きな期待と同時にいくつかの課題も提示しています。政府は、この戦略を「経済と環境の好循環」を生み出すための産業政策と位置づけ、世界トップレベルの技術競争力確保を目指しています。2021年の策定以降、2024年に至るまで、政府は技術開発の進展や国際的な環境変化に応じて柔軟に戦略を見直し、実効性の高い施策を随時発表し、予算を投入しています。例えば、2021年3月にはグリーンイノベーション基金事業の基本方針が策定され、2021年4月には温室効果ガス削減目標の引き上げが行われるなど、政府の強いリーダーシップが示されています。
この戦略がもたらす経済効果については、2050年の時点で約290兆円、雇用効果は約1,800万人と試算されており、新たな雇用創出と産業発展への期待が高まっています。ロードマップとしては、電力部門の脱炭素化を最重要視し、再生可能エネルギーの最大限導入、水素・燃料アンモニアの活用、次世代熱エネルギーの導入、原子力技術の発展など、具体的な道筋が示されています。非電力部門についても、電化の推進や水素化、CO2回収技術の活用など、多様な施策が展開されます。しかし、技術革新の加速や巨額の投資、国際的なサプライチェーンの構築、国民の理解と行動変容など、多くの課題も存在します。これらの課題を克服し、政府、企業、国民が一体となって取り組みを進めることで、日本は持続可能な社会の実現と国際競争力の向上を両立させ、世界のグリーン経済をリードする存在となることが期待されています。
【まとめ】グリーン成長戦略を理解し、2050年カーボンニュートラルに向けて取り組みを進めよう!
グリーン成長戦略は、2050年カーボンニュートラル実現という日本の大きな目標達成に向けた、産業と環境の好循環を生み出すための重要な政策です。本記事で解説したように、この戦略はエネルギー、輸送・製造、そして私たちの生活に密接に関わるその他の重要分野を含む14の広範な産業を対象とし、それぞれに具体的かつ野心的な実行計画が定められています。
企業経営を担う皆様にとって、グリーン成長戦略は単なる環境規制への対応ではなく、新たなビジネスチャンスと成長の機会と捉えるべきものです。政府は2兆円のグリーンイノベーション基金をはじめとする税制、金融、補助金などの多様な支援策を用意し、企業の脱炭素化への挑戦を強力に後押ししています。これらの支援策を積極的に活用し、自社の事業におけるCO2排出量削減はもちろんのこと、新たな技術開発やビジネスモデルの変革に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献し、企業の競争力強化にも繋がるでしょう。
2050年カーボンニュートラルという目標は決して容易ではありませんが、この戦略を深く理解し、具体的な取り組みを推進することで、日本経済の未来を切り拓くことができます。ぜひ、貴社においてもグリーン成長戦略を経営戦略の中心に据え、次なる成長への一歩を踏み出してください。