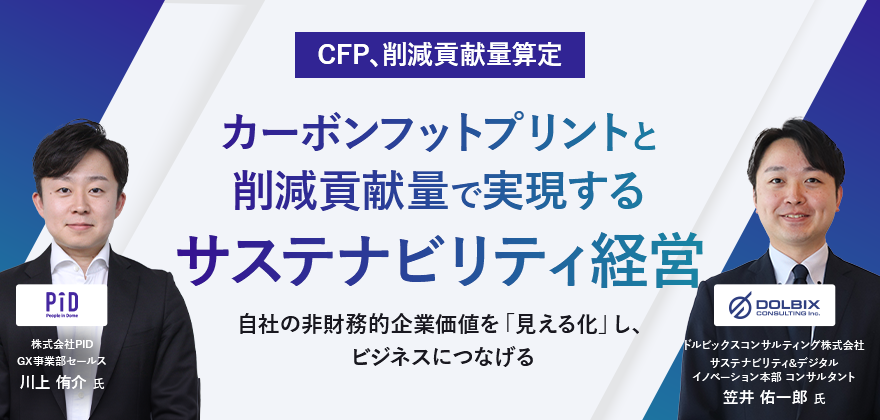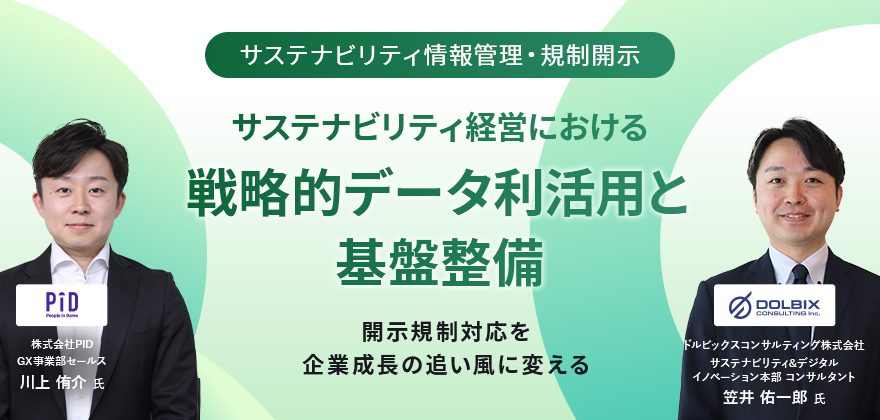プラスチックをリサイクルする取り組みは、地球規模での環境問題解決に向けて不可欠な方法として、世界中で注目されています。しかし、その現状にはまだ多くの課題が存在し、各国や企業による積極的な取り組みが求められています。
この記事では、プラスチックのリサイクル方法をわかりやすく具体的に解説し、現在の課題、そしてそれらを克服するための国や企業の動きについて掘り下げていきます。
ウェビナー開催中! 詳細・お申し込みは画像をクリック!
プラスチックのリサイクルで生まれるもの
プラスチックをリサイクルすると、様々な製品に生まれ変わり、資源の有効活用につながります。リサイクルされたプラスチックは、新たなプラスチック製品として利用されるだけでなく、化学製品の原料などにも再利用されることが可能です。
例えば、衣料品やペットボトル、洗剤などの容器といった身近な製品から、公園の遊具やベンチ、土木シート、コンテナ、フェンスなどの大規模なもの、さらには自動車部品や建材としても活用されています。また、製鉄に用いられるコークスや、アンモニア、溶媒として使われるメタノール、ベンゼン、トルエン、キシレンといった化学製品の原料になることもあります。プラスチックの種類によって何になるかは異なりますが、資源が無駄にならないよう多岐にわたる商品へと再製品化されています。
リサイクル可能な素材
プラスチック製品は全てがリサイクルできるわけではありませんが、リサイクル可能な素材には特定のマークが付与されています。日本においては、「資源有効利用促進法」により、飲み物などのペットボトルやプラスチック製容器包装に識別表示マークの表示が義務付けられています。ペットボトルの場合は「PETマーク」、それ以外のプラスチック製容器包装には「プラマーク」が表示されており、これらのマークが付いている商品は積極的にリサイクル回収ボックスに出すことが推奨されます。
PETマークは、ポリエチレンテレフタレート(PET)素材に用いられ、飲料用や調味料用のペットボトルなどに多く見られます。ボトルとキャップの両方がリサイクルの対象となる場合が多いです。プラマークは、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリ塩化ビニール(PVC)、低密度ポリエチレン(LDPE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)など、PET以外の様々なプラスチック素材の容器包装に付けられています。例えば、ポリ袋、お弁当の容器、食品用トレイ、包装に使われる袋などに広く利用されています。
しかし、薄いラップフィルムや3cm以下の小さなプラスチック製品は、リサイクル施設の機械に巻き付いたり挟まったりして故障の原因となるため、リサイクルできない場合があります。また、人形のガラスケース、CDケース、楽器やカメラのケースなど、中身の商品と分離されても不要にならないものは容器包装に該当しないため、リサイクルマーク表示の対象外となります。 識別マークの表示は、印刷やラベル、刻印によって行われ、サイズも定められています。複合素材の場合、最も多く使われている材質のマークが表示されるなど、表記方法にはいくつかのルールがあります。これらのマークを理解し、適切に分別することが、効率的なプラスチックリサイクルには不可欠です。
廃プラスチックとは?
廃プラスチックとは、使用後に廃棄されたプラスチック製品や、その製造過程で発生したプラスチックのかす、さらに廃タイヤを含むプラスチックを主成分とする廃棄物のことを指します。具体的には、家庭から排出されるペットボトル、食品トレイ、ビニール袋、調味料ボトルなどの「一般系廃プラスチック」と、製造業、建設業、農業といった産業活動から排出される「産業系廃プラスチック」に大別されます。一般系廃プラスチックは市町村が収集・処理を行う一般廃棄物に分類され、通常は「プラ」マークや「PET」マークが付いています。一方、産業系廃プラスチックは、産業廃棄物として扱われ、合成ゴムくず、合成樹脂くず、合成繊維くず、発泡スチロール、PPバンド、コンテナ類、建築資材、事務用品などが含まれます。
廃プラスチックは、リサイクル、焼却、埋立処分などの方法で適切に処理されますが、その多くはマテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクルの3つの主要なリサイクル手法によって再利用されています。これらの廃プラスチックを適切に分別し、リサイクルを進めることは、資源の有効活用や環境負荷の低減に繋がり、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みとして位置づけられています。
プラスチックの主なリサイクル手法
プラスチックのリサイクル方法には、大きく分けて3つの手法があります。これらは「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」と呼ばれ、それぞれ異なるプロセスと特徴を持ちます。これらの3つのリサイクル方法を適切に使い分けることで、廃プラスチックを効率的に再利用し、環境負荷を低減することを目指しています。
マテリアルリサイクル -新たな製品へ
マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを物理的に処理し、新たな製品の原材料として再利用する手法です。具体的には、回収された使用済みプラスチックを洗浄し、粉砕、溶融、成形といった工程を経て、再びプラスチック製品の原料に戻し、新しい製品に加工します。この方法で作られる製品は多岐にわたり、文房具、ペットボトル、コンテナ、ベンチ、フェンス、遊具、土木シート、さらには衣類や食品用トレーなど、私たちの身近なものに生まれ変わります。
マテリアルリサイクルの大きなメリットは、プラスチックの性質を維持したまま再利用できるため、比較的高品質な製品を製造できる点、そして資源の有効活用とCO2排出量削減に大きく貢献する点です。石油から新たにプラスチックを製造するよりも、使用する資源やエネルギーが少なく済むため、二酸化炭素の排出削減が期待できます。
しかし、課題も存在します。廃プラスチックが汚れていると、リサイクルされた製品の品質が低下してしまうため、食品や飲料のプラスチック容器などは、リサイクルに出す前にきれいに洗浄する必要があります。また、再生工程でプラスチックの品質劣化が起こる場合があり、繰り返し再生できる回数には限りがあるという点も課題として挙げられます。さらに、すべてのプラスチックがマテリアルリサイクルに適しているわけではないため、選別や不純物の除去に手間がかかることもあります。
ケミカルリサイクル -原料として再利用
ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的な処理によって分解し、元の化学原料や石油製品に戻して再利用する手法です。この方法は、物理的に再利用するマテリアルリサイクルでは難しい、混合されたプラスチックや汚れたプラスチックでも処理できる点が大きな特徴です。
ケミカルリサイクルの主な手法には、「油化」「ガス化」「高炉原料化」「コークス炉化学原料化」などがあります。油化は、プラスチックを再び石油に戻す技術であり、生成された油は石油化学製品の原料として利用されます。廃プラスチックをガス化して化学工業の原料に再利用する技術も確立されています。また、製鉄所の高炉やコークス炉で、プラスチックを還元剤や化学原料として利用する方法も普及しています。ケミカルリサイクルで生成された原料は、新しいプラスチック製品、食品包装材、自動車部品、塗料、接着剤など、多岐にわたる製品の製造に利用されます。何度でもバージン品(新品の原料)と遜色ない品質の製品を再生できるため、循環経済の観点から注目されています。
一方で、ケミカルリサイクルは設備投資や運搬費用に大きなコストがかかることが課題として挙げられます。過去には油化法で大型設備が稼働していたものの、コストパフォーマンスの悪さから撤退した事例もあります。しかし、近年では、よりコストパフォーマンスの高い技術開発が進められており、出光興産や三菱ケミカルグループなどが新たな商業生産設備の稼働を目指すなど、実用化に向けた取り組みが活発化しています。
サーマルリサイクル -熱エネルギーの活用
サーマルリサイクルは、廃プラスチックを燃焼する際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水利用などに活用するリサイクル方法です。この手法は「熱回収」や「エネルギー回収」とも呼ばれ、廃棄物の量を効果的に減らし、同時にエネルギーを有効利用できる点が特徴です。プラスチックは紙類と比較して発熱量が大きく、石炭や石油に匹敵するエネルギー資源として注目されています。そのため、焼却時に発生する熱や蒸気を利用して発電したり、温水プールや暖房の熱源として活用したりすることが可能です。また、固形燃料化(RPF、RDF)して利用されることもあります。 サーマルリサイクルのメリットとしては、異物が混ざったプラスチックや、選別が難しいプラスチックも処理できるため、広範囲な廃棄物を対象にできる点が挙げられます。また、最終処分場の延命や、化石燃料の使用削減にも貢献します。
しかし、デメリットとして、燃焼時に二酸化炭素(CO2)やダイオキシンなどの有害物質が排出される点が挙げられます。近年では、技術の進歩や規制の強化により、有害物質の排出量は抑制されているものの、完全にゼロにすることは難しいのが現状です。そのため、環境負荷の評価が難しいという課題も抱えています。また、国際社会、特にOECDの基準では、サーマルリサイクルはリサイクルとして認識されていないことが多い点も留意する必要があります。
プラスチックリサイクルの国内外の状況
プラスチックリサイクルは、地球規模の環境課題として認識されており、日本だけでなく世界各国でその現状と課題に取り組んでいます。各国が直面するプラスチック廃棄物の量やリサイクル割合、そしてその方法には違いが見られ、それぞれが異なる課題を抱えながら解決策を模索しています。
日本のリサイクル率と世界の比較
日本のプラスチックリサイクル率は、表面上は高い水準を維持していますが、その内訳を見ると課題が見えてきます。2022年時点で、日本のプラスチック有効利用率は87%と高い数字を示していますが、これはサーマルリサイクル(熱回収)が大半を占めているためです。具体的には、2020年のデータでは、マテリアルリサイクルが22%、ケミカルリサイクルが3%、サーマルリサイクルが60%という内訳でした。しかし、経済協力開発機構(OECD)などの国際的な基準では、サーマルリサイクルはリサイクルとして認識されていません。この基準に基づくと、サーマルリサイクルを含まない日本のプラスチックリサイクル率は、2022年時点で約25.2%にとどまります。
一方、ヨーロッパ(EU)では、2016年のリサイクル率が約31%(エネルギーリカバリー42%)でした。EUの主要国では、ドイツが39%と比較的高いリサイクル率を示し、埋め立てを法律で禁じているため、埋立率は実質ゼロです。しかし、他の主要国では埋立比率が30~46%と高いところもあります。かつて日本は、廃プラスチックを中国をはじめとするアジア諸国に輸出することでリサイクル率を高く保っていましたが、2018年に中国が廃プラスチックの輸入規制を開始したことを皮切りに、バーゼル条約の改正などにより、多くの国が廃プラスチックの輸入規制を強化しました。この変化は、日本が国内でのプラスチック循環システムを構築する必要性を高める要因となっています。
日本のPETボトルのリサイクル率は85%と高く、欧州の42%、米国の21%と比較しても非常に優れていますが、これは容器包装以外のプラスチックを含む全体の傾向とは異なります。総じて、日本は高い有効利用率を誇るものの、国際基準に合わせたマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの割合を増やすことが、今後の重要な課題となっています。
日本のプラスチックリサイクルにおける課題
日本のプラスチックリサイクルは、高い有効利用率を維持しつつも、いくつかの重要な課題に直面しています。その中でも特に、サーマルリサイクルの割合が課題として挙げられます。プラスチックを燃焼させて熱エネルギーとして利用するサーマルリサイクルは、日本のプラスチック有効利用率において一定の割合を占めています。サーマルリサイクルはCO2を排出しますが、埋め立てと比較して環境負荷を抑えられるという見方もあります。国際的にはリサイクルとしての位置づけが議論されることもありますが、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルに適さない廃プラスチックの処理方法として活用される事例も存在します。
また、回収と分別の難しさも課題です。プラスチック製品には様々な種類があり、素材ごとに適切に分別しなければ、高品質なリサイクルが難しくなります。汚れや不純物が付着していると、マテリアルリサイクルの品質が劣化し、再利用が困難になることもあります。特に、薄いラップフィルムや3cm以下の小型プラスチック類は、リサイクル施設で処理が難しいとされています。さらに、リサイクルにかかるコストの高さも問題です。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルは、高度な技術や設備を要するため、処理費用が高くなる傾向があります。過去には、ケミカルリサイクルの油化技術で大型設備が稼働していましたが、採算性の問題から撤退した事例もあります。加えて、海外への輸出規制が強化されたことも、日本のプラスチックリサイクルにとって大きな課題です。これまで日本は廃プラスチックを海外に輸出していましたが、中国をはじめとする国々が環境問題への意識の高まりから輸入規制を導入したため、国内での処理体制の強化が急務となっています。
これらのプラスチックリサイクルの課題を解決するためには、環境省をはじめとする国や自治体が、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの技術開発と普及を促進し、回収・分別システムの改善、そして市場の形成を支援することが不可欠です。また、有害物質の排出を抑制しながら、資源のループを構築し、全体の環境負荷を低減する取り組みが求められています。
企業がプラスチックリサイクルに取り組むメリット
企業がプラスチックリサイクルに積極的に取り組むことは、環境負荷の低減だけでなく、多岐にわたるメリットをもたらします。これは、現代の経営において持続可能性と経済性の両立を図る上で非常に重要な利点となります。
まず、環境負荷の低減は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で不可欠です。プラスチックをリサイクルすることで、新たなプラスチック製品を製造する際に必要となる天然資源の消費を抑制し、埋め立て処分される廃棄物の量を削減できます。これにより、地球温暖化の原因となるCO2排出量の削減にも貢献します。特に、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルは、ゼロからプラスチックを製造する場合と比較して、CO2排出量を大幅に削減することが可能です。
次に、コスト削減も大きなメリットです。プラスチック廃棄物をリサイクルによって有価物化することで、新たな原材料の購入費用を削減できる場合があります。また、廃棄物の処理にかかるコストも減少することが期待されます。これは、企業にとって直接的な経済的利点となります。
さらに、プラスチックリサイクルへの取り組みは、企業のイメージ向上に繋がります。環境意識の高まりとともに、消費者や取引先は環境に配慮した企業を高く評価する傾向にあります。リサイクルへの積極的な姿勢を示すことで、企業ブランド価値を高め、顧客からの信頼を獲得し、競争優位性を確立できるでしょう。加えて、リサイクルの取り組みは、企業内の業務内容のスリム化や新たなビジネスモデルの構築にも繋がり得ます。リサイクル可能な素材を優先する製品設計や、効率的な回収・選別システムの導入は、サプライチェーン全体の見直しを促し、生産効率の向上やコスト削減に寄与します。将来的には、資源循環型のビジネスモデルを確立することで、カーボンニュートラルの達成に向けた貢献も期待されます。
国内企業によるプラスチックリサイクルの事例
国内の企業も、プラスチックリサイクルの推進に向けて多角的な取り組みを進めています。これらの取り組みは、環境負荷の低減だけでなく、新たなビジネスチャンスの創出にも繋がっています。
旭化成株式会社は、商品のQRコードを読み取ることで再生プラスチック利用率が分かる技術の試験を進めています。これにより、消費者の再生プラスチック利用への意識を高め、リサイクル行動を促すことを目指しています。
イオン株式会社は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルといった3つの主要なリサイクル方法を組み合わせ、資源循環を推進しています。例えば、ペットボトルの水平リサイクル(使用済みペットボトルから新しいペットボトルを製造)や、衣類、食品用トレーなどへのダウンマテリアルリサイクルに取り組んでいます。
出光興産の子会社であるケミカルリサイクル・ジャパン株式会社は、千葉事業所隣接エリアに年間2万トンの処理能力を持つ油化ケミカルリサイクル商業生産設備を設置し、2025年度の商業運転開始を目指しています。回収した使用済みプラスチックから生成油を生産し、原油に替わる原料として石油精製装置や石油化学装置で「リニューアブル化学品」を製造する計画です。
これらの事例は、メーカーだけでなく、小売業や自治体など、様々な立場からプラスチックリサイクルの促進に貢献していることを示しています。自動車部品や建材など、幅広い用途でのリサイクルも進められており、プラスチックの循環利用を多方面から推進しています。
【まとめ】プラスチックのリサイクルに積極的に取り組もう!
プラスチックリサイクルは、地球規模の環境課題を解決し、持続可能な社会を実現するために不可欠な取り組みです。マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルという3つの主要な方法を通じて、廃プラスチックは新たな製品やエネルギーとして再利用されています。しかし、特に日本ではサーマルリサイクルの割合が高く、国際的なリサイクルの定義との乖離や、分別・回収の難しさ、コストの問題など、依然として多くの課題が存在しています。
これらの課題を克服するためには、国や行政による法制度の整備や技術開発の支援に加え、企業の積極的な取り組みが不可欠です。国内企業による先進的なリサイクル技術の開発や、再生プラスチックの利用促進の事例は、その可能性を示しています。企業がプラスチックリサイクルに取り組むことは、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や企業イメージの向上にも繋がり、持続可能なビジネスモデルを構築する上でのメリットも大きいものです。私たち一人ひとりがプラスチックの分別を徹底し、再生材を使った製品を選ぶといった行動も、大きな一歩となります。
プラスチック問題は、一部の専門家や行政だけの問題ではなく、企業、そして消費者である私たち全員が主体的に関わることで解決へと向かいます。ぜひ、この記事で得た知識を活かし、自社や個人でできる範囲から、プラスチックのリサイクルに積極的に取り組んでいきましょう。